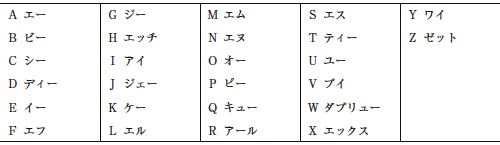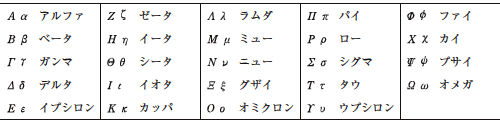大学で声を出して講義をしたり、絶対に間違えたくない公式資料を裁判所に出したりという仕事を続ける中で、とくに化合物や生物の種名などをどうカタカナに置きかえているのか、自分でもアヤフヤだった部分や間違って覚えていた部分に気づかされるようになった。
アルファベット
また、欧語のアルファベットについても化学会の字訳基準がある。
ローマ文字については、むしろ英語の発音が推奨されている。たとえばDMTは「ディーエムティー」であって、「デーエメテー」とは読まない。
モノアミン酸化酵素阻害薬はMAOIと略すが、これは「エムエーオー阻害薬」ということは少なく、「マオ阻害薬」あるいは「マオイ」と呼ばれることも多いという。
日本語の独特な文字としてカタカナがある。もっぱら他の言葉を置きかえるための文字である。
生物の学名
生物の学名に使われるラテン語については、日本人による変換プログラムが作られている。
シビレタケ属のラテン語名である「Psilocybe」は、学名としては「プシロキベ」だが、通常は「シロシベ」という呼び方が使われる。あるいは「psilocin」という物質名についても、原語に近い表記なら「プシロシン」だが、やや英語訛りの「シロシン」も使われるし、麻薬及び向精神薬取締法には「サイロシビン」と書かれている。どれが正しいというわけではないのだが、学術論文や裁判資料の中では、混乱が起こらないようにしたいものである。
記述の自己評価 ★☆☆☆☆
(随想的な草稿です。学術的に価値のある部分は、切り出して別記事にします。)
デフォルトのリンク先ははてなキーワードまたはWikipediaです。「」で囲まれたリンクはこのブログの別記事へのリンクです。詳細は「リンクと引用の指針」をご覧ください。
*1:ISOコモンネーム「コモンネーム字訳 Ⅲ. 字訳基準表」(2022/08/26 JST 最終閲覧)
*2:JapanKnowledge「凡例 1.見出し語について」『デジタル化学辞典 第2版』(2022/08/26 JST 最終閲覧)
*3:JapanKnowledge「凡例 1.見出し語について」『デジタル化学辞典 第2版』(2022/08/26 JST 最終閲覧)